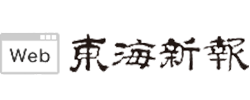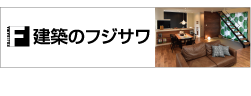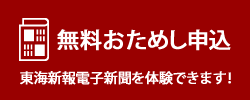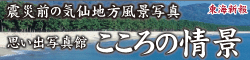食の復興「深いつながり」を、住田の農業者らが自主発信/岩手生産者の会(別写真あり)
平成28年7月14日付 1面

東日本大震災を機に広がった人脈を生かし、地道に生産されている岩手産食材の良さを首都圏消費者の心にどう響かせるか──。住田を含む県南部を中心とした農業者有志による「岩手生産者の会」が、自主的に新たな取り組みを始めた。これまで交流がある首都圏の料理人が住田産のニンニクをはじめ旬の食材を扱う機会をつくり、そこに生産者が出向き幅広い層の人々とともに味わいながら、魅力や今後の展開を語り合う。同会では「深くつながり、よりよいものを生み出すきっかけになれば」と、力を込める。
震災以降の人脈生かし
東京で交流 新たな試み
今月2日、東京都渋谷区初台のフランス料理店「レストランアニス」。同会初のイベント「岩手の梁川ひつじと野菜」が開かれ、首都圏のマスコミや食肉流通関係者、生産者ら約30人が訪れた。
住田町下有住で「火の土にんにく」を生産し、企画の中心的な役割を務めた佐藤道太さん(31)。「半夏生(7月1日)を迎え、農作業がひと段落つき、農家が手を休める時期。みなさんで料理を堪能し、楽しい会にしたい」と語りかけた。
店内は木の温もりにあふれ、比較的カジュアルな雰囲気が広がる。この日のメーン食材は、奥州市江刺区の梁川地区で生産されている仔羊。ニンニクはもちろん、さやいんげんやズッキーニも住田産が用意された。
腕をふるったのは、とくに肉料理に定評がある同店シェフの清水将さん(40)。カウンターの前にある鉄板上で羊肉を長時間じっくりと焼き上げ、独特の香ばしさが来訪者を歓迎した。
「梁川ひつじ」はもともと、遊休農地などの景観保持に向けた〝草刈り要員〟だったというが、震災の影響で一時放牧ができなくなり、ラム肉としての販売を模索した経緯がある。独特の臭みが少なく、柔らかな食感への評価は高まりつつある。
また「火の土にんにく」は50~60年前、農協組織が現在の八幡平市から住田町に導入した。「香辛料としてではなく、生でそのまま食べてほしかった」と清水さん。ニンニク特有のにおいは控えめで、マイルドさが特徴とされる。仔羊のテリーヌに添えられ、来訪者はフワリとした食感から優しさを感じる味わいを楽しんだ。
岩手からは生産者ら10人余りが出向いたが、交通費をはじめすべて自己負担。現段階では行政などから補助を受けず、イベント費用は味わったすべての参加者が出し合った。
この日の会費は1人1万3000円。誰もが遠慮せず、料理やワインを残すことなく存分に味わい、会話を弾ませた。
5年4カ月前の発災以降、清水さんをはじめ多くの著名な料理人が炊き出しといった被災者支援活動に尽力し、地域の1次産業を担う生産者とも交流を深めた。料理人が被災地を訪れる機会は少なくなったが、当時出会った人々との絆はついえていない。
交流を生かした復興を見据え、生産者がまず県内でネットワークを構築する。生産者自身が発信者となり、料理人や消費者をはじめ参加者全員でこれからの展開を考える場を自主的に生み出す。
高品質であっても、量や種類が少なければ首都圏での発信力は弱い。各料理店でも岩手産を扱う割合は少量にとどまっている中、季節に合わせたイベントを企画することで岩手産のまとまりを生み出し、そこに集う人々に新たな発見や感動の機会をもたらす。
終了後、清水さんは「この日のメニューは岩手に行き、食材やつくられている方々と直接ふれあったことがヒントになっている。生産者が主体となって進める取り組みは、これからの日本の食文化のあり方を考えても重要」と語った。
同会では今後も料理人、首都圏在住者、生産者が料理を囲みながら自由に語らう場を企画する方針。佐藤さんは「食材をつくった人が東京に来て、顔を合わせる場をこれからもつくりたい」と話す。