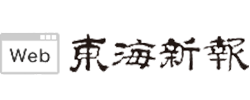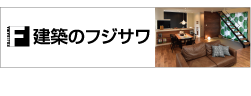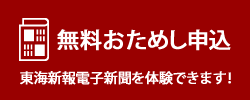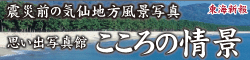つなぐ/東日本大震災と住田の心① 遺族として・住民として㊤
平成29年2月19日付 1面

東日本大震災から、間もなく6年を迎える。気仙両市では高台移転が進展し、かさ上げ地でも事業所再建の動きが広がるなど、復旧・復興への動きは前へと進み続ける。一方で、隣接する住田町でも発災以降、多くの人々が悲しみに向き合い、新たな行動を始めるなど、濃密な時間を過ごしてきた。「あの日」からの思いに耳を傾け、言葉をつなぎたい。(日曜日掲載)
「大変だったな」が辛かった
昨年12月10日、住田町役場で「熊本復興応援プロジェクト・住田町の小さな小さなクリスマス会」が開かれた。主催した世田米・中沢公民館の一員で、1カ月以上前から準備を重ねた岩城和彦さん(56)。着ぐるみをまとって運営にあたり、表情にはやさしさがにじみでていた。
子どもたちの小さな手が、一つずつエコバッグに飾りつけを施し、メッセージを添えた住田町産のスギ板プレートをキーホルダーとして取り付ける。仕上がると笑顔があふれ、歓声が上がった。装飾したエコバッグは、熊本地震被災地に贈った。
「俺は定年まで、家と会社の往復が続くと思っていた。外に出て、人に会うのがいやだった。でも、出会いの積み重ねによって、ここまで押し上げられてきた。今は、息子も『頑張ってるね』って声をかけてくれるかな」
‡‡
「きょうは寒いぞ」
「雪が降ってきたな」
毎朝、和彦さんは自宅の居間に置いている写真に、心の中で語りかける。6年近く、無意識に続けてきた。
大津波は、当時高田高校2年生だった三男・直俊さんの命を奪った。住田町は浸水を免れたが、当時気仙両市など沿岸部にいた住民13人が犠牲となった。
震災がなければ今、直俊さんは社会人として活躍している年代。和彦さんにとっては、高校生のままであり続ける。語りかける言葉の内容にも、大きな変化はない。
平成23年3月11日、直俊さんは登校日だった。学校の入試対応もあり、午後1時ごろに校舎を出たが、住田方面のバスは3時台まで待たなければならない。2時46分に大きな揺れが襲った直後、家族と「市役所にいた」「大丈夫」とメールを交わしてから、連絡がとれなくなった。
一方、和彦さんは「あの時」、勤めていた世田米の自動車整備工場・販売会社にいた。大地震の揺れが収まり落ち着きを取り戻したあと、知人から停電したと聞いた特別養護老人ホーム・すみた荘に向かった。寒さが増す中、発電機で復旧しようと配線作業にあたったほか、商店街を回るなどして灯油で暖を取れる反射式ストーブの確保にも奔走した。
夜、自宅に戻り、直俊さんが帰っていないことを初めて知った。すぐに高田町に入り、翌朝、避難所で担任教諭から「いない」と告げられた。それからは毎日、捜し続けた。
「あの時は、地獄の日々だった」。遺体安置所に名前が出ていると聞いたのは、くしくも和彦さんの誕生日、3月18日だった。
‡‡
震災直後、連日新聞が報じた「亡くなられた方」。同22日付に、住田町への死亡届提出者として唯一、直俊さんの名前が出た。
人口約6000人の小さな町は、住民同士のつながりが深い。自らが語らなくても、すぐに広まった。
悲しみに直面する近しい人に、何かを伝えたい──。震災直後、住田で暮らしていた多くの人々が、そう思った。和彦さんは、買い物など外に出た先々で「大変だったな」と声をかけられた。
「俺がどのくらい大変か、本当に分かることができるのか。あの言葉が、つらかった」
今ならば、抱いた思いを振り返り、口に出せる。当時は、怒りに似た感情を心の中だけでおしとどめた。気遣って声をかけてくれた住民を、責めることはしなかった。
家の中に、閉じこもっていたかった。やり場のない絶望と喪失感が、全身をめぐり続けた。クリスマス会を催し、子どもたちと笑顔で会話を交わす日がやがて来るとは、想像もできなかった。