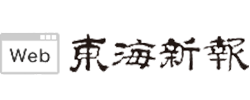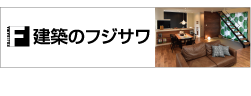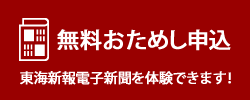4年ぶり新作『幽霊屋敷のアイツ』、大船渡市在住の小説家・川口さん
平成29年8月6日付 8面

デビュー作『虹色ほたる~永遠の夏休み~』が大ヒットを記録した、大船渡市在住の小説家・川口雅幸さん(46)=時光堂店主=はこのほど、4年ぶりとなる新作児童書『幽霊屋敷のアイツ』(アルファポリス/税抜き1600円)を刊行した。作家としては「決して書くまい」と〝封印〟してきた東日本大震災について、今回初めて作中に描写。発災から6年が経過したいま改めて、子どもたちや災害の非当事者にその経験を伝えるとともに、大切な誰かを亡くした人に対しては「この作品が〝レクイエム(鎮魂歌)〟になれば」という願いを込めた。
震災経験も織り込む
川口さんは平成19年に『虹色ほたる~永遠の夏休み~』でデビュー。世代を超えて話題となり、40万部を超えるロングヒットを記録しただけでなく、長編アニメ化もされた。続く『からくり夢時計~DREAM∞CROCKS~』『UFOがくれた夏』もヒット。現代劇を描きながら、どこか懐かしさ漂う作風で人気を博している。
4作目となる本作では、これまで「書くつもりはない」と明言していた6年前の大震災について初めて触れた。自宅、店ともに被災し、自身も九死に一生を得る体験をした川口さん。震災はあまりにも生々しい出来事であり、自らが得意とするファンタジー世界の題材にはそぐわないと考えていた。
しかしここ数年、新しい物語の構想がひねりだせずにいた中、思いついたアイデアに震災の出来事を絡めた途端、ストーリーが前へ前へ転がり出したという。複雑な気持ちになりながらも、被災地に暮らす当事者ならではの描写を織り交ぜ、物語をつむぎあげていった。
作品の舞台は平成24年の夏。大震災発生の翌年だが、主人公の少年・燈馬が暮らす町も、燈馬が祖母を訪ねて訪れる別の町も、東北の被災地とは無縁の場所だ。子どもたちは前年の大地震のことなどすっかり忘れて日常を取り戻し、楽しい夏休みを送っている。
しかし、燈馬が不思議な出会いをした少女が、実は大津波で家族を失っていることが分かる。大震災と、それを経験していない子どもたちとの距離感や、想像もつかないほど悲しい思いをした子が身近にいると分かった時の戸惑いが、手に取るように伝わってくる。
出版社側は当初、「東日本大震災」という固有名詞を使うことをはじめ、近年起きたばかりの悲劇を登場させることには難色を示していたという。編集者からは「何か別の事故だとか、架空の災害に置き換えては」という提案もあった。
しかし、あれほど「避けたい、書きたくない」と考えていた川口さん自身が、「いつまでも腫れ物に触るように扱ったり、つらい出来事だからとフタをしてしまうのは違うのではないか」と思うようになっていった。
起きてしまったことは、なかったことにはできない。大切なものを失いながらも、現実を受け止め、必死に、前向きに生きていかねば──自身の思いが、物語のテーマとも合致した。
東日本大震災は物語の重要なエピソードとして登場するが、「震災の話というわけではない」と川口さん。人の死を通じて「懸命に生きる」ことの意味を問いかけ、自らの手で生きる道を選ぶ子どもたちの姿を描いた。
「子どものころから藤子不二雄作品が大好きだった」といい、これまでと同様、本作でも〝日常の中のSF(すこし・ふしぎ)〟を盛り込んだ。どこにでもいるような少年少女の物語に一さじ加えられた「ファンタジーのエッセンス」と、持ち味である「どこかノスタルジックな筆致」は健在。悲しい出来事もつづりながら、物語全体は温かく優しいものに仕上がっている。
前作、『UFOがくれた夏』では第二次世界大戦について触れた。その時も「大災害と戦争は別のものだが『決して忘れてはならない』という点では共通している」と語った川口さん。「東日本大震災は日本人にとってすごく大きな出来事だった。それでも、報道されなくなれば忘れられていく。時間が少したったからこそ書けたのだと思うし、いま残しておかねばと思った」といい、「私も、この作品を出せていなければ、前へは進めていなかったかもしれない」と振り返る。
川口さんは「津波で犠牲となった方、被災者の方に対する私なりのメッセージを込めた〝レクイエム〟。地元の方にも読んでいただきたい」と呼びかけ、「もっと多くの人に届けるためにも、この作品が映像化されることが夢です」と期待を寄せていた。