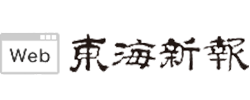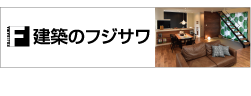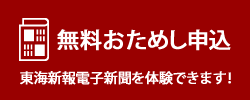東日本大震災7年/まちと人、〝成長〟著しく
平成30年3月11日付 1面

日本を、世界を大きく揺るがせた平成23年の東日本大震災発生から、きょうで丸7年を迎えた。震災の年に生まれた子らはすでに小学生となり、発災当時10代だった若者たちも社会人としてそれぞれ自立し始めているほどの年月だ。あの大災害を経験していない子どもや住民も増えた。瞬く間のようでありながら、確かに流れた7年の歳月。住宅再建や防災、まちづくりにかかるハード整備にめどが立ちつつある半面、新たな壁も住民の前に立ちはだかる。震災でより深刻さを増した課題を克服し、まだまだ続く難局を乗り越えていくためにも、若い力とその声をしっかり受け止められる地域にしていかねばならない。
発災8年目迎えた気仙のこれから
大震災津波により、大船渡では340人、陸前高田では1557人の市民が犠牲となった。11日には気仙各地で慰霊と追悼の行事が予定され、多くの市民らがそれぞれの場所であの日を思う。
今も大船渡79人、陸前高田202人の行方が分からない。県警が平成24年以降毎月行ってきた月命日(11日)近辺の捜索活動でも、この5年余り目立った手がかりが見つかっておらず、新年度からは沿岸各署の「随時捜索」に切り替わることも決まった。
時間の経過とともに、行方不明者の発見や身元不明者の特定は難しくなる。一方、数年越しで新事実が明らかになるケースもないわけではない。県内では先月、新たなDNA鑑定方法によって3人の身元が判明したと報じられた。年数で区切るのではなく、不明者家族らの心情に添った丁寧な対応がこれからも求められる。
住まいを失った人たちの住宅再建は、一歩一歩、着実な前進を見せる。家を失い、住宅再建が困難な市民らのために整備された災害公営住宅は、気仙両市で計画された36団地(大船渡25、陸前高田11)の計1696戸(大船渡801戸、陸前高田895戸)がすべて完成しており、被災者の入居が進む。
大船渡市では昨秋までに防災集団移転促進事業(防集)366戸の全造成を完了。陸前高田市では計画戸数490戸のうち9割以上の整備が済み、30年度内に同事業が完了する見込みとなっている。
応急仮設住宅の撤去・集約も本格化。大船渡市では市内37カ所に整備された仮設住宅団地が、1月末時点で7カ所にまで減った。学校グラウンドに建設された団地はすでに撤去済み。住田町では3団地のうち、2カ所が残っている。
陸前高田市では53カ所の団地が整備されたうち、今も33カ所に仮設住宅が立つが、30年度は22カ所にまで減少予定。児童生徒が通う学校に建設された団地は29年度内に撤去・集約が行われ、秋ごろから順次、学校への〝返還〟が始まる見通しだ。
4月には、移転先の整備待ちといった事情がある人に限り仮設の入居期間を延ばすことができる、「特定延長」制度が導入される。特別な理由がなく転居の見通しが立っていない世帯に対しては、必要な関係機関と連携しながら、個々の事情に合わせ、次の住まいへ移れるよう支援を進めていく必要がある。
2月1日現在の両市の人口は、大船渡市が3万6704人、陸前高田市が1万9082人で、昨年の同時期より大船渡で1123人、陸前高田で729人減少した。発災直前の23年3月1日との比較では、大船渡が3675人の減、陸前高田が4139人の減と、人口減少課題はより深刻さを増す。
定住人口の増加を目指し、官民それぞれがI・Uターン促進にかかる取り組み、婚活事業などを推し進める。さらに、移住・定住にも結びつく「交流人口」の拡大にも力を入れる。
震災後、気仙地域と深くかかわりを持つようになった人々との交流は、今もあちこちで続いている。物理的に離れていても〝心的距離〟が密な人たちは、何年にもわたって気仙へ足を運び、地域に活気をもたらしてくれる。昨春、両市それぞれに新市街地の目玉となる商業施設がオープンしたことで、まちなかには新たな人の流れも生まれた。
ハード整備に着地点が見え始め、まちのベースとなるものは整いつつある。あとはそこに鮮やかで魅力ある〝絵〟を描いていくため、今後はよりいっそう内外の英知を結集しまちづくりにあたっていくことが肝要だ。
若い力が着実に育つ
昨年春に新潟の大学を卒業し、県立大船渡病院(伊藤達朗院長)で臨床検査技師として働く村上実希さん(23)=陸前高田市高田町出身=は今年、古里へ戻ってから2回目の春を迎える。
5歳から同市の順道館岩﨑道場で柔道を始めた。小中学生時代から何度も全国大会へ出場していたため、高校進学の際はスポーツ推薦の声もかかったが、母・君子さん(当時53)は柔道での進学に反対。学業成績も優れていた村上さんは、競技の名門でもある盛岡中央高校へ学力特待生として入学した。
東日本大震災の発生は、そのわずか1年後。ちょうどオーストラリアへの短期留学中で、日本の惨状は人づてに聞いて知った。
実家は大津波で全壊し、君子さんと、2番目の姉・優佳さん(当時30)の行方は今も分からない。家を失った被災者であり、震災遺児でもある一方、そう呼ばれる自分の立場には「実感がない」と村上さん。「母親がいなくてかわいそう」とみられることにも違和感がある。
「自分の人生。後ろ向きにはとらえていない」。そうきっぱり語る。
一方、幼いころから母に言われ続けた「手に職をつけなさい」という言葉は心に染みついていた。もともと医療職を目指していた村上さんだったが、柔道で痛めたひざの手術のときに知った臨床検査技師という職業に興味を持ち、同技師と臨床工学技士、二つの資格を同時取得できる新潟医療福祉大へ進んだ。
進学にあたっては、東北の震災遺児・孤児の進学を支援する公益財団法人みちのく未来基金(仙台市、長沼孝義代表理事)からの助成も活用。金銭的な援助より、村上さんがありがたいと感じているのは、月1回の面談をはじめとした同財団の親身なサポートだった。
財団スタッフや〝みちのく生〟同士のつながりも強い。今も仙台の事務所に顔を出しておしゃべりしたり、後輩にあたる生徒たちの面談を手伝ったりする。「去年の12月には毎週通ってましたね」と村上さん。その笑顔が一番輝くのは〝みちのく〟について語る時だ。
県下最大の津波被害を受けた陸前高田には親を亡くした児童生徒が多く、今も毎年新たに同郷のみちのく生が増える。面倒見のいい村上さんは、同じような進路を目指す子の相談に乗ることもある。
就職を決める際、岩手へのUターンは「意識した」という。「地震も津波も経験していない。中学までの友達が避難生活を送っているのに、自分は盛岡にいて何もできなかった」という後ろめたさがそうさせた側面はあるが、この1年で仕事にも慣れ、一人でやれることも増えてきた。今は自分なりの目標も胸に秘める。
DMAT(災害派遣医療チーム)の活動にも興味を持つ。いずれにしろ、学ばねばならないことは山積みだ。「今は勉強の日々。慢心せず、本当にやりたいことを見極めていければ」と村上さん。大学の恩師に言われ続けてきた「臨床検査技師は、迅速かつ正確に検査結果を出すのが仕事」という言葉を胸に、一人前となることを目指す。
(12面に関連記事)