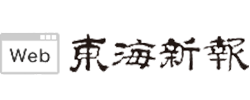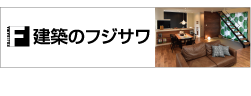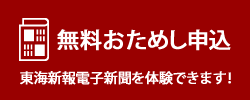震災7年6カ月―忘れえぬ思い⑦千田 尚順さん(73)
平成30年9月11日付 7面

絵筆に思い込める
別れと出会いきっかけに
大船渡市日頃市町字郷道の千田尚順さんは、東日本大震災の発生後、自宅のアトリエで水彩画を描くようになった。「絵を描いている間は無心になれる」と、柔らかな表情を浮かべる千田さん。手に持つ筆が動くたび、キャンバスに描かれたグラデーションが少しずつ印象を変え、絵に〝命〟が吹き込まれていく。
絵を描くようになったきっかけは、高田高校で講師をしていた時の同僚や生徒らとの別れ、そして、震災後に出会った人たちとのふれあいだった。
「同僚や生徒を津波に〝もっていかれた〟あと、たくさんの出会いがあった。みなさんと出会わなければ、絵を描き始められなかったと思う」と、千田さんは振り返る。
◇
千田さんは北上市二子町出身。青森県の弘前大学教育学部を卒業後、英語教諭として岩手県内の高校で教べんをとった。平成17年、大船渡高校の校長を退職後、高田高校で8年間講師を勤めた。
あの日、千田さんは同校で生徒の進路指導を行っていた。これまで感じたことのない大きな揺れに襲われ、課外授業や部活動などで校舎内にいた生徒、教職員らとともに玄関前の駐車場に出た。
混乱のさなか、一人の女性教員の声が響いた。社会科の教諭で、水泳部の顧問を務めていた小野寺素子さん(当時29)が、「プールにいる生徒たちが心配なので行ってきます」と叫び、海から100㍍ほどの場所にあった施設に車を走らせた。
「高さ7㍍の津波が押し寄せる」という放送がラジオから流れたのはその直後。千田さんが小野寺さんの姿を見たのは、その時が最後となった。
生徒とともに校舎裏の高台に避難した千田さんは、大津波が高田松原のマツをなぎ倒し、市街地をのみ込む光景に言葉を失った。
発災から7年半が過ぎたが、小野寺さんの行方は今も分かっていない。「一緒に仕事をした期間は4〜5年ほど。若いながらも指導力、行動力に優れ、爽やかな人柄で生徒によく慕われていた」と語る千田さん。「津波の情報をもっと早く知っていたら…」──心のつっかえは、震災から7年半たった今も残ったままだ。
◇
24年7月、千田さんは小野寺さんの実家がある北海道小樽市に向かい、小野寺さんの両親を訪ねた。小野寺さんの思い出の品を飾っている部屋に案内されると、高さ30㌢ほどの木彫りの仏像が目に入った。
この仏像は、小野寺さんの母親が震災後に高田高校を訪れた際、同校の敷地で偶然見つけ、持ち帰ったもの。優しい目や、きりっと締まった口元などが小野寺さんにそっくりで、〝再会〟を果たしたような気がしたという。
小野寺さんの実家をあとにした千田さんは、近くを通る小樽運河に立ち寄った。「小樽は画家がよく題材にする所なんですよ」。震災前、職場での何気ない会話の中で、小野寺さんがそう言った。あの時の言葉がよみがえり、手持ちのカメラで運河の風景を撮影。日頃市に戻り、水彩の筆で写真の風景を模写した。
「絵は昔から興味があったが、道具をそろえるだけで、なかなか始めるきっかけがなかった。(亡くなった)妻にもよく『いつになったら描くの』と言われていたが、小樽から帰ったあの日、描きたいという思いがわいた」と語る。
その後、陸前高田市の画家・熊谷睦男さんの指導を受け、千田さんは水彩画の世界に没頭。気仙の絵画グループ「彩光会」や「七虹会」にも入会し、今年6月、初の個展を大船渡市内で開いた。
「同僚や生徒を失った悲しみは消えないが、いつまでも立ち止まっていてはいけない。無心になって打ち込めるものを見つけられてよかった」と千田さん。「自分が今、何を描きたいのか、何をしたいのか、テーマを決めて前に進みたい。きっと、素子さんや生徒たちも喜んでくれる」と顔を上げ、今日もキャンバスに向かう。(月1回掲載)