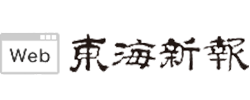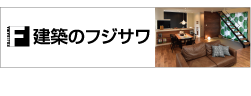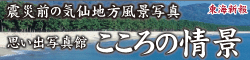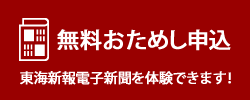特別インタビュー「気仙からプロ選手を」、小笠原満男さん(鹿島アントラーズ)
平成31年1月12日付 7面

本紙は、昨年末に現役引退を表明したサッカー元日本代表・小笠原満男さん(39)=鹿島アントラーズ、大船渡高卒=に単独インタビューを行った。これからのことや、気仙地方に対する思いを聞いた。
──引退表明から時間を置いてみて、今の心境は。
小笠原 もっとさみしくなるかなと思っていたけど、意外とすっきりしている。これから次の道に進めることが楽しみでもある。東北、岩手、大船渡への恩返しについても、もっと考えていきたい。
──これまでもすでに、赤崎グラウンドの整備など十分すぎるほど力を尽くしてもらっている。高校時代の3年間しか暮らしていない気仙に、そこまで思いをかけてくれるのはなぜか。
小笠原 この場所で育ててもらったという思いがある。妻が陸前高田出身なので卒業後もよく帰っていたし、高校のときは高田松原のサッカー場も使わせてもらった。
気仙のために何かできればという思いはプロになってからもずっと持っていたが、東日本大震災という最悪な出来事が、実際に動きだすきっかけになってしまったのは正直なところ。ただ、最悪な出来事をプラスに変えるため力になれたら、と。子どもたちの「運動する場所がない」という言葉が胸に刺さり、突き動かされた点も大きい。
自分もいろんな人のお世話になり、子どもだった自分を変えてもらった。経験したことを子どもたちに還元し、さらにその子らが次の世代へ返すというサイクルが生まれていけばと思う。
──大船渡高校にはただ一人、盛岡からの越境入学。16歳で見知らぬ環境に飛び込んだ当時を振り返ってみると。
小笠原 (大高サッカー部監督だった)斎藤(重信)先生に教わりたいという気持ちもあったが、ちょうど思春期だったし、親元を離れてみたかったというのが本音。家で口うるさく言われるのがいやだった。ところが、高校では斎藤先生という親以上に厳しい人がいたわけで…。
最初は知らない場所にいるさみしさもあった。でも、仲良したちと〝ぬるま湯〟につかっていては成長しない。厳しい環境に身を置き、トライすることが必要だと思った。それは海外に行ったときも同じように感じたこと。
1年生の初めはサッカー部に入るという同級生も数人しかいなく、野球部やらバレー部やら、友達の友達に声かけて誘ってもらったりした。だから、それまでサッカー経験がないメンバーとも一緒に全国目指して…。強豪校に入って続けてもよかったんだろうけど、「ここでやってやる」という自信もあったし、なんだか漫画のストーリーみたいでおもしろかった。
──卒業後、アントラーズ入りし、すぐ頭角を現した印象がある。
小笠原 それはない。自分は決して優れた選手ではない。高校まで通用していたものがプロに入って通じなくなり、いきなり鼻っ柱をへし折られた感じだった。日本代表になったといっても、本大会のメンバーから外されたり…「一つ結果を出したくらいでいい気になったらだめだ。上には上がいる」と思ってきた。
ただ、自分はすごく〝人〟に恵まれたと思う。岩手でも、アントラーズに入ってからも。「お前はいらない」と言われたらそれで終わりの厳しい世界で、俺を信じて契約してくれた人もいる。そうした恩に報いるためには、強くなるしかない。
引退前のシーズンは、「1回も練習を休まないこと」を自分に課した。休みたかったことだってあったが、その間にもほかの選手は上達していく。「うまくなりたい、ポジションをとりたい」と思っていたから、絶対毎日やるぞ、と。
(キャプテンとして)だれよりも一生懸命に練習しよう、まずは一番頑張っていることを姿勢で示すんだというつもりでずっとやってきた。
──現役は退くが、アントラーズに、ひいてはサッカーに今後どのようにかかわっていきたいか。
小笠原 まだ具体的には言えないが、もちろんアントラーズのためにも何かしたい。サッカーを通じて自分にできることはまだあると思うし、わくわくしている。
──気仙とのかかわり方については。
小笠原 赤崎グラウンドでも、もっとできることがあると思うし、地元と相談しながら取り組みを発展させていきたい。
これまでも、赤崎グラウンドには関東などから子どもたちを招いたりして、震災について知ってもらうきっかけづくりをしてきた。秋田や盛岡など雪深い地域からも「使いたい」と申し出がある。気仙に人を呼び込み、こちらでお金を使ってもらったり、教訓の伝承にも役立ててもらえる施設だと思う。
そもそも「ここからまたプロアスリートを」という思いが発端となったプロジェクト。野球の大谷翔平選手の活躍を見ているとこっちまでうれしくなるように、次の岩手の子どもたちのためにも、プロになるような選手が育ってくれることを願っている。
ずっと応援してくれた人たちへの感謝も込めて、自分にできることを見つけ、気仙とずっとかかわっていくつもりだ。(聞き手・鈴木英里)