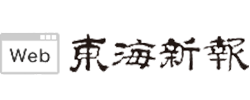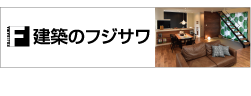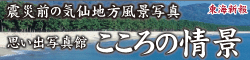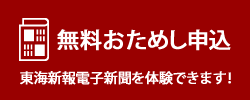東日本大震災10年2カ月/川遊びの魅力 息子に伝える 高田町で被災の佐々木さん 亡き母の思い出や教訓とともに(別写真あり)
令和3年5月11日付 1面

東日本大震災の発生から、きょうで10年2カ月。陸前高田市高田町には先月、「川原川公園」がオープンし、遊歩道を歩く市民や水辺に降りて遊ぶ親子連れなどでにぎわうようになった。東日本大震災で壊滅的な被害を受け、町内会解散を余儀なくされた同町川原地区に生まれ育ち、毎日のように川原川で遊んでいたという同町の佐々木正也さん(46)=NPO法人・桜ライン311職員=は、津波で母を失った経験を経て、一人一人に防災意識を根付かせるための活動に携わりながら、自分の子どもたちにも水辺での楽しい思い出を作ってほしいと願う。
亡き母の思い出や教訓とともに
発災時、佐々木さんは北上市のメーカーに勤務しつつ、生活拠点は地元に置き、両親、長男の凌さんと、川沿いの自宅で暮らしていた。震災当日は仕事が休みで、陸前高田で大地震に見舞われたという。
両親と避難所へ向かう前、隣人の高齢女性にも声をかけた。しかし、足を悪くしていた女性は避難したがらず、「行く、行かない」の押し問答があった。佐々木さんは母の香子さん(当時61)から「消防団の活動があるんだから行ったほうがいい」と言われ、ひとまず両親より先に消防屯所が隣接する川原地区会館へ向かった。
到着すると、すでに団の車両は出動したあと。避難者たちが海の状況についてささやき合う中、高田松原方面に土ぼこりが上がるのが見えた。
「津波が(国道)45号を越えたってよ」──そんな声を耳にした時、目の前まで津波が迫っているのが見えた。佐々木さんは父の姿を見つけ、抱えるようにして山道を駆け上った。振り返った時には大津波がすべてをのみこみ、先ほどまでいた会館も黒い波の下に沈んでいた。
後に、香子さんが一度は避難したものの、家に戻ったことが分かった。「父の薬を取りに戻ったのか、やはり隣のおばあちゃんを置いていけないと思ったのか」。それは今も分からないが、「誰かのための行動であったろう」と佐々木さんは思う。「それぐらい、優しい人だった」。
母をはじめ、大切な人たちが亡くなった実感はなかなかない。地震直後に会い、互いに「よう」と手を上げて無事を確認したはずの幼なじみも犠牲となっていた。
「さっきまで生きていたのに、一緒にいたのに、人ってこんな簡単に死んでしまうんだ」。
災害に対する意識がもっと高ければ。もっと強く「逃げよう」と母に伝えていれば──そんな後悔を抱く佐々木さんが現在所属する「桜ライン311」は、津波到達地点にサクラを植えることで、市民のみならずボランティアで関わる人たちにも防災意識を根付かせようと活動している。
今は22歳になり、仙台市で暮らす凌さんには「地震や津波だけが災害ではないから」と繰り返し伝えてきた。
27年に生まれた次男の蒼良君(5)にも、口を酸っぱくして避難の大切さを教えている。同時に〝楽しいこと〟も伝えたいという。
それは、自分が何よりも大好きな川原川の魅力。凌さんも小さいころは震災前の川で遊んでいた。
佐々木さんは「『危ないから近づくな』ではなく、『こうすると危ない』ということを経験から学んでほしい」といい、川に入って魚を捕まえるような楽しみを蒼良君にも教えてあげたいと、完成後、週1回は同公園へ遊びに来ている。
実は、公園内の遊歩道部分には実家のあった場所も含まれる。
会ったことのない祖母の仏壇に毎日手を合わせる蒼良君に、「津波が来る前はここにパパの家があったんだよ」と伝えてもピンとは来ない様子だが、「防災意識のことも、川で遊んだことも、大きくなった時に『そんなこと話していたな、こんなことがあったな』と思い出してもらえればいい。親に言われ続けたことって、けっこう胸に残っているものだと思う。自分がそうだったから」と佐々木さんは語り、楽しそうに遊ぶわが子を優しく見つめた。