インタビュー気仙2025ー⑥大船渡湾冷凍水産加工業協同組合代表理事組合長・濱田 浩司さん(66) 新たな意識で難局打破へ
令和7年1月26日付 1面
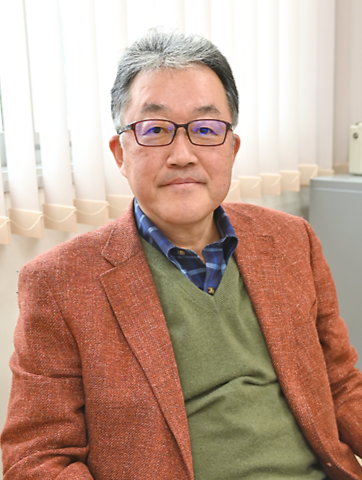
――本年度、大船渡ワンレイのトップに就任した。水産業の状況も含めて、昨年1年間を振り返っての所感を。
濱田 組合自体は、冷蔵施設での保管事業をメインに、販売、購買などの事業を展開している。経営的には魚の保管業務が増えていくことが望ましいが、近年は主要魚種の不漁によって魚が取れず、組合員が疲弊しているような状況が続き、難しいかじ取り。新しい魚種への切り替えや、新規事業を始めるとは言っても、資金面や今後の漁況などの見通しが難しく、なかなか一歩が踏み出せないのではと思う。〝待つ〟仕事、経営ではなく、新たなものに積極的に取り組む意識を持って、前に進んでいかなければならない。
――取り扱いの主力であるサンマをはじめ、さまざまな魚種の不漁が叫ばれている。水産業の現状は。
濱田 年間で見ると、暮れから春にかけてのイワシ、2~4月のイサダ、9~12月のサンマが主な取り扱いになる。大船渡を代表する魚のサンマは、2万㌧以上取れた時代と比べると、漁獲減が著しい。昨年の数量は少し持ち直し、船は良かったが、加工はサイズや値段の関係で難しい状況だった。イワシは前年よりものが取れており、浜から魚が揚がれば、それを冷凍するだけでもある程度の収入になる。「陸もよし船もよし」という状況はなかなかないが、少しでも多くなってくれれば。
──水産加工原料の不足と価格高騰、円安における輸入原料コスト上昇など、原料調達が難しい状況が続く。
濱田 世界的に原料が足りなくなっている状況に加え、軍事情勢の激化、さらには円安で輸入物は不利な状況にある。大きな原料の一つであるペルーのアメリカオオアカイカは昨年6月から壊滅状態で、原料価格が2倍以上に高騰するなど、危機感を持って見ている。海外原料もうまく立ち回って使っていかないと、今後が苦しくなる。
──水産加工業を取り巻く環境が厳しさを増す中で、組合が果たす役割をどう捉えているか。また、現状を打破するために必要な意識は。
濱田 かつては組合が間に入って売り込み、交渉をしたり、組合を通じて魚を売った時代もあったが、インターネットの発達、普及で企業が直接取引を行うようになり、それぞれで独自の販路を築いている。本県でも大船渡を含めて四つの組合があったが、現在は大船渡、釜石の二つになり、時代が移り変わる中で組合の必要性も変化してきているという認識でいる。
不漁はその通りにしか捉えられないが、魚が来るのを待っている人が多いのではと感じる。事業転換をしようにも、原料、加工技術、機械設備に加えて販路も確保しなければならない。今までのものを捨てて切り替えられるか、新しいことに挑む姿勢も必要だ。
たとえば、購買事業でサンマやイサダの冷凍ブロックをカットして売るだとか、ふるさと納税の活用、使わなくなった施設を利活用して新たな取り組みができないかなど、活路を見いだすために考えを巡らせている。待っているだけでは商売にならない。先行きが見えない中だが、自ら変えていく意識を持っておくことは大切。
──水産加工業界を支える組織として、まちの水産振興に向けて今年1年の抱負を。
濱田 個人の経営者が集まってできている組合であり、皆が同じ仕事をしているわけではなく、全てはフォローできないにしても、国や県の補助事業を紹介したり、組合員の仕事に合わせた情報提供、サポートなど、できることはどんどんやっていきたい。組合員に了解を得たうえで、新しいことにも取り組み、それが工場の稼働や生産販売につながればいいと思っている。組合員にも喜んでもらえるような取り組みを、意見を聞きながら一緒に進めていきたい。(聞き手・菅野弘大)








