8年ぶりに大幅見直しへ 町の地域防災計画 25日までパブコメを実施
令和7年2月1日付 7面
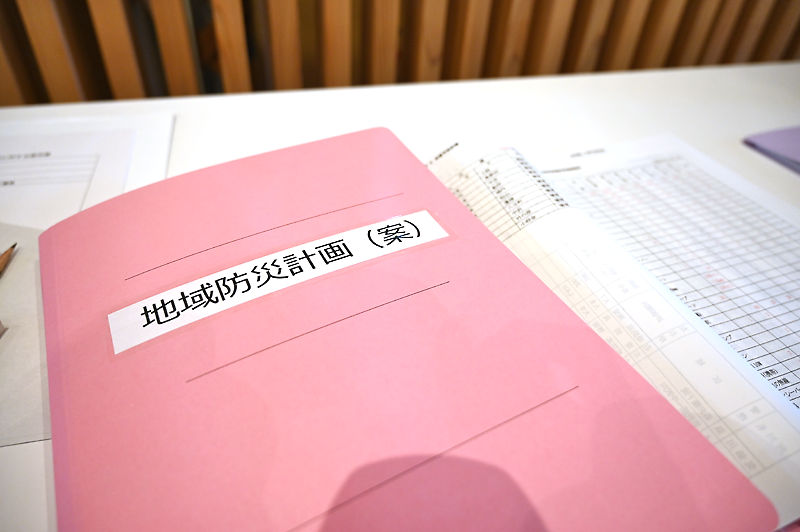
近年、大規模な自然災害が各地で頻発する中、住田町は8年ぶりに地域防災計画の大幅見直しを行い、防災対策の強化・充実を図る。障害者や独居高齢者、外国人など災害弱者への対応、防災意識高揚に向けた取り組みなどを新たに盛り込んでおり、25日(火)まで素案を公表してパブリックコメントを実施し、町防災会議での協議を経て3月中に策定する見込み。(清水辰彦)
町の地域防災計画は、災害予防、食料・生活必需品供給などさまざまな計画を盛り込んだもの。平成28年の更新以降、年数が経過し、その間にも各地で自然災害が発生していることも踏まえ、県の地域防災計画とも整合性を図りながら計画を大きく見直した。
計画は4章構成。1章は総則、2章は災害予防計画、3章は災害応急対策計画、4章は災害復旧・復興計画についてそれぞれ記載しており、災害弱者への対応、感染症対策、防災教育充実、被災者の生活支援などについて新たな取り組みを加えている。
計画に新規で盛り込んだ項目をみると、2章第1節「防災知識普及計画」では、「住民に対する防災知識の普及」の項目の中に、「『自らの命は自らが守る』という意識を持ち、自らの判断で避難行動をとることおよび早期避難の重要性を住民に周知」などと追加。災害時には「自助」「共助」の意識が重要となるから、平時からの個々への意識付けを図る。
同じく第1節の中の「児童、生徒に対する教育」の項目には、「地域の防災力を高めていくため、一般住民向けの専門的・体系的な防災教育訓練の提供、学校における防災教育の充実、防災に関する教材(副読本)の充実を図る」「学校において消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育が推進されるよう努める」と追加。児童・生徒にも、災害を〝わがこと〟として捉えてもらうよう、機運を醸成する。
第1節にはこのほか▽国際的な情報発信▽防災と福祉の連携▽専門家の活用──の3項目も新たに盛り込んでいる。
同章第6節「避難対策計画」内の「避難場所の整備等」には、「避難場所等を指定する際は、広域避難等の用にも供することについて定めるなど、他の市町村からの避難者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定しておくよう努める」や、感染症対策として「避難者1人当たりの必要面積をおおむね2平方㍍以上」とも設けた。
加えて、「指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な障がい者、医療的ケアを必要とする者等の要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所を指定するよう努める。特に、医療的ケアを必要とする者に対しては、人工呼吸器や吸引器等の医療機器の電源の確保等の必要な配慮をするよう努める」など災害弱者への対応についても定めている。
3章第15節「医療・保健計画」には、「災害中長期における医療体制」について新たに明記。大規模災害時などにおいては、災害派遣医療チーム(DMAT)撤退後、避難所における巡回診療や被災地の病院等の診療のために、引き続き医療救護班等の派遣が必要である場合は、気仙医師会、気仙歯科医師会などの関係団体に対し応援の継続を要請することや、被災者の心のケア等を実施するために、災害派遣精神医療チーム(DPAT)の精神医療活動を継続することとしている。
計画案は、役場交流プラザや各地区公民館のほか、町ホームページで閲覧できる。
問い合わせは町総務課防災管財係(℡46・2112)まで。








