発見・通報の状況明らかに 大規模林野火災消防庁長官調査報告書 乾燥や強風下での延焼拡大も整理
令和7年7月17日付 1面
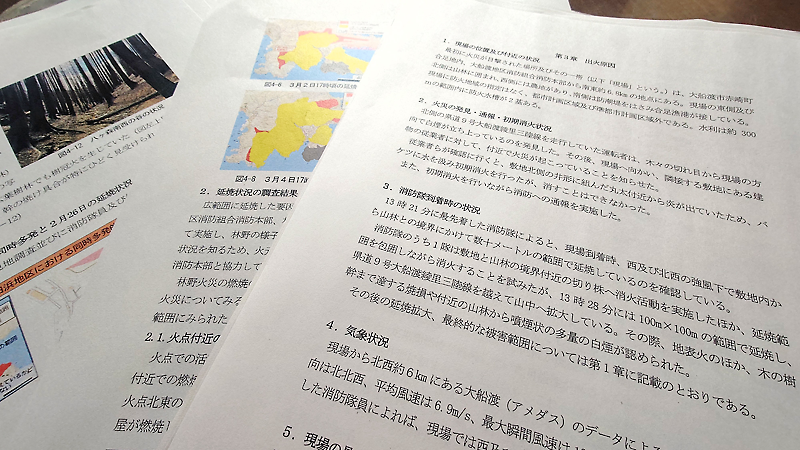
【一部既報】消防庁が15日に示した大船渡市大規模林野火災に関する消防庁長官の火災原因報告書では、出火した2月26日の発見・通報時の状況や、平成以降の林野火災で最大となる3370㌶に及んだ延焼状況や要因も取りまとめた。降水量が少なく林野内の可燃物が乾燥し、局地的な風やリアス海岸の複雑な地形も影響して広範囲に至ったとする。原因特定には至らなかったが、多様な自然条件が複雑にからみ合った状況が分かり、改めて火災予防の重要性が浮かび上がる。(佐藤 壮)
大規模林野火災の出火時刻は不明だが、消防覚知時刻は2月26日午後1時2分。報告書では、これまで市の会見などで詳細な説明がなかった発見・通報・初期消火状況も記載している。
火点は合足漁港付近に位置する。北側の主要地方道大船渡綾里三陸線を走行していた運転者が、木々の切れ目から現場方向に白煙が立ち上るのを確認。現場に向かい、隣接する敷地にある建物の関係者に知らせた。
敷地北側に「井形」に組まれた丸太付近から出ていた炎を目にし、バケツに水を汲んで初期消火を行うとともに、消防に通報。同21分に到着した消防隊は、強風下で、建物敷地内から山林との境界部にかけての数十㍍での延焼を確認した。
消防隊は延焼範囲を包囲する形で消火を試みたが、同28分には100㍍四方の範囲に拡大し、主要地方道を越えた。地表火だけでなく、木の樹冠まで達する焼損に加え、山林からは噴煙状の白煙が見えたという。
報告書ではさらに、火災に影響を与えたとみる気象状況を、出火場所から約6㌔北西に位置する大船渡アメダスのデータから整理。今年2月は観測を開始した昭和38年8月以降で降水量が2番目に少なく、2月としては最少。12月~2月の冬季3カ月間でも、過去3番目に少なかった。
また、出火日までの31日間に0・5㍉を超える降水はなく、直前8日間は降水量は観測されなかった。さらに出火日の湿度も低く、気象庁は乾燥注意報を発表。同日正午前に83%あった湿度は急激に低下し、出火直前の午後1時には44%、同3時には最小の38%に至った。
以降、3月4日までの6日間は、同2日を除き最小湿度は40%未満に。最小湿度は午後の観測が多かったという。
出火から5日間は日照時間が平年値を上回り、特に2月26日と27日は、午前よりも午後の方が日照時間が長く、南西斜面の可燃物の乾燥を助長した可能性に言及している。
これらの要因により「谷部に厚く堆積したものも含め、林内の可燃物は乾燥して燃焼しやすい条件であったと考えられる」とまとめた。
出火日の最大瞬間風速は18㍍に及び、翌日の2月27日と4日目の3月1日も同程度の強風に見舞われた。2月28日には、南風が入ったことで綾里富士の南麓にまで到達していた火線が追い風を受けて斜面を焼け上がり、北方向に延焼範囲が広がった。
火災は合足地域の火元から強風を受け、火元から1・2㌔東に離れた八ヶ森方面に拡大。八ヶ森の南西に位置する杉林の谷で、広範囲に樹冠火を含む激しい燃焼が発生し、消防の覚知から約40分後の午後1時40分ごろには、濃煙が立ち上がった。
濃煙はさらに東に流れ、八ヶ森から約2㌔離れた田浜地域で同2時前後には、少なくとも3件の飛び火が発生した。同3時ごろには、東西約7㌔の範囲にまで延焼が拡大した。
住家被害は90棟で、このうち全焼54棟。非住家は136棟で、全焼は121棟。綾里の小路、港両地域、赤崎町の外口地域などで建物の延焼が発生した。現地調査が行われた綾里の港地域では、9カ所の出火点が確認され、いずれも飛び火によるものと考えられる。
地元消防本部や消防団、県内応援隊が消火活動を展開したほか、空き地や道路、建物の防火性能を生かして延焼を食い止めた。2月26日午後3時30分には消防屯所北側でぼやが発生し、放置すれば岩崎地域方向の住宅地にも延焼した可能性があったが、初期消火で拡大を防いだ。
3月3日には、赤崎町の外口地域の建物にも火の手が及んだ。樹木の下や枯れ草などに飛び火のものとみられる焼け跡が多く確認され、消防庁では「建物被害は主に飛び火によるもの」との認識を示す。
林内では主に、地表火を主体に燃え上がった。斜面の傾斜と局地的な風の影響を受け、リアス海岸の複雑な地形も重なり、多方向に広がった。
消防庁と林野庁による「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」は来月、最終回の会議を開く。今月15日の会議では、火災警報の発令基準や検討会としての報告書も議題にしており、教訓を踏まえた予防の方向性などがどのようにまとめられるか注目される。








